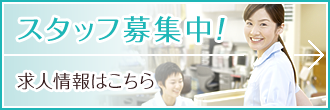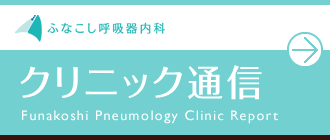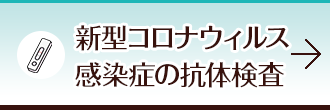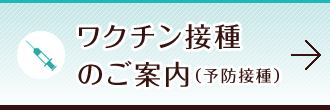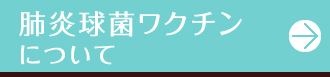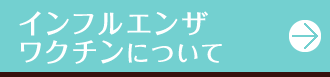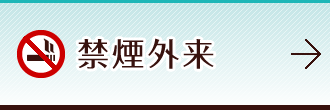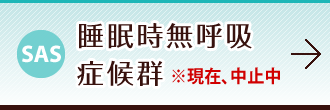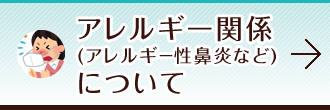3月当初はかなりまだ寒かったですが、次第に暖かくなっています。花粉症や黄砂を始めとする粉塵の飛散などにより、喘息を始めとする呼吸器系の病気が増悪する時期になって来ています。
-
3月5日(水)は、産業医講習会が大阪市内で行われました。2題の講演がなされました。一題目は『最近の労働衛生行政の動向』のタイトルで、大阪産業保健総合支援センター副所長の上田卓司先生が講演されました。労働安全衛生法に基づく産業医の取り組みやその職務を説明されました。二題目は『職域での復職判断と法的解釈、判例などを通じて』のタイトルで、弁護士の白石浩亮先生が説明されました。病気休職とその後の復職に際しての注意事項を学びました。
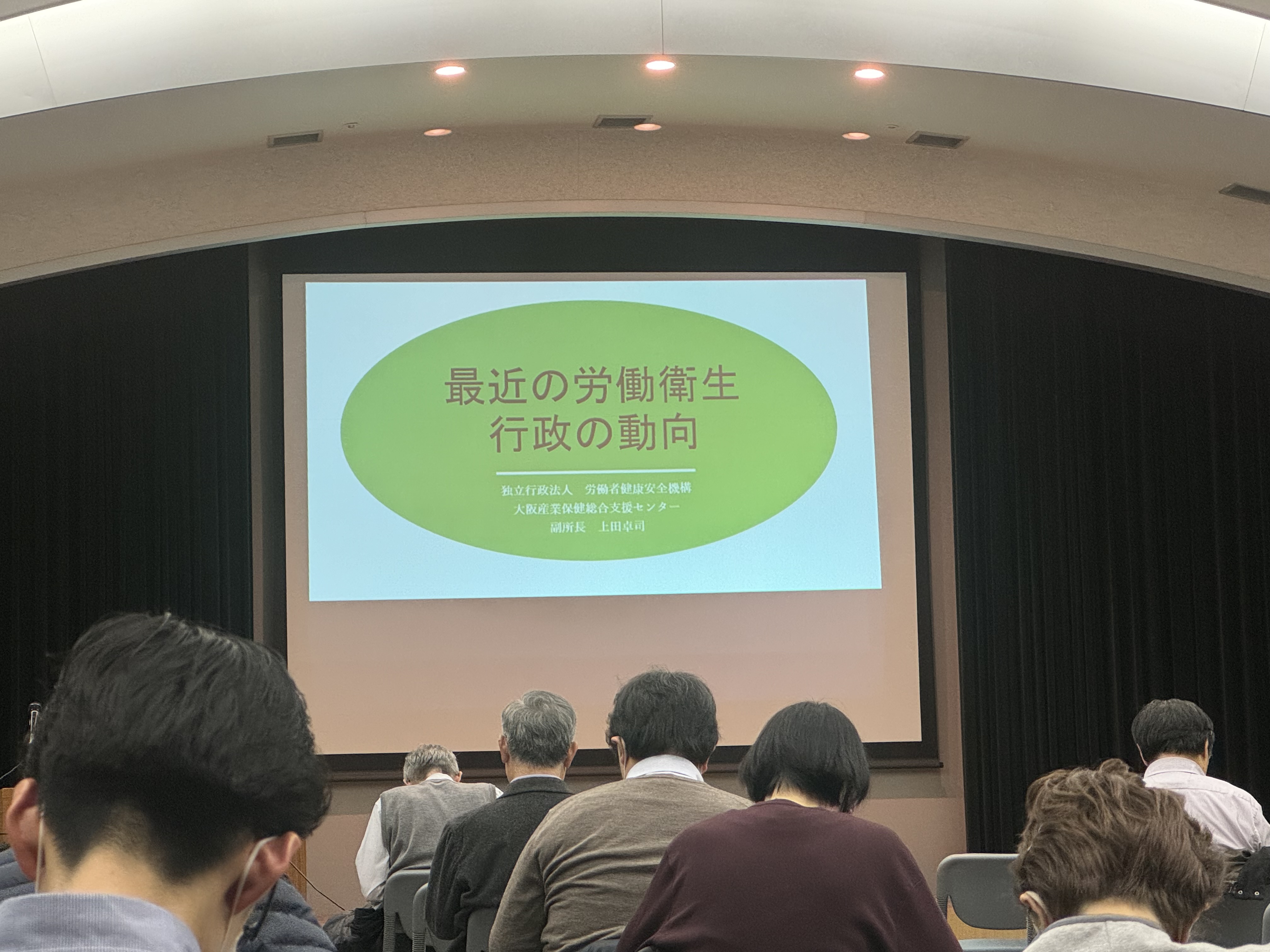
-
3月上旬は、呼吸器内視鏡学会の専門医大会のweb視聴ができました。2月22日に大津市で開催されたもののオンデマンド視聴できました。現在はいわゆる気管支鏡を触る機会は無くなりました。しかし呼吸器内科診療において、患者様を病院にご紹介して、その後に気管支鏡検査を受ける患者様も少なくありません。気管支鏡の進歩は日進月歩ですので、最新の医療技術を知るにはいい機会です。特に3つほど興味ある講演がありました。
1つ目はいわゆる超音波内視鏡です。『EBUSーTBNAとEBUSーIFB』のタイトルで、大阪公立大学呼吸器内科の中井俊之先生が講演されました。タイトルのEBUSーTBNAは、肺門と縦隔リンパ節生検に対する超音波気管支鏡ガイド下生検のことです。EBUSーIFBは、穿刺孔を作成して行う超音波気管支鏡ガイド結節内鉗子生検のことです。
2つ目は『気管支バルブ治療の現況と今後の展望』のタイトルで、聖マリアンヌ医科大学呼吸器内科の峰下昌道先生が説明されました。気管支バルブ治療という気胸等に用いる方法が勉強になりました。今から10年以上前にも肺機能の良くない方の難治性気胸の治療は困難でしたが、最新のアプローチを説明されました。バルブは以前には時に歯科素材から手作りすることもありました。今は専門的な医療会社から作成された市販されているバルブができており、時代の差を感じました。
3つ目は『極細径・細径気管支鏡を用いた末梢肺野病変診断』のタイトルで、名古屋医療センター呼吸器内科の沖昌英先生が講演されました。肺野の非常に小さい結節の一部採取に際して、かなり細い気管支鏡でヒットさせる手技方法を解説されました。


ふなこし呼吸器内科 院長 船越俊幹