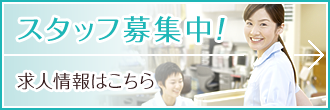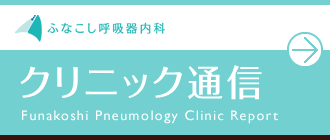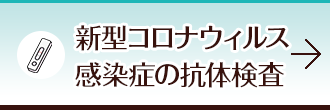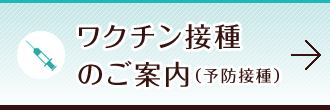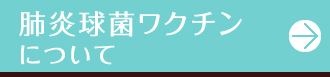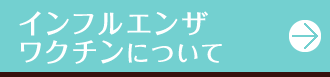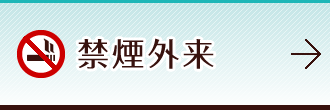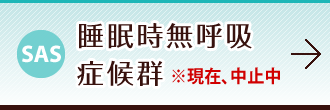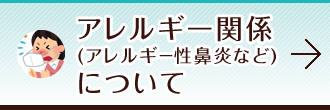7月後半も酷暑に至っています。当院前の院外廊下は10分も滞在できません。何回もお願いして申し訳ありませんが、院内待機場所に限りがあり、特に発熱のある方が院内で滞在できないこともあります。通常は院外廊下でお待ちしていただいておりますが、それができません。発熱の方のご受診は、できるだけ車等で来院いただいて、待ち時間は車等で待機していただくようにお願いいたします。
-
7月中は6月末に開催された気管支鏡学会総会をwebで視聴できました。
備忘録のためにも、興味ある講演を述べていきます。『肺がん診療における呼吸器内視鏡医が知るべき細胞診』のタイトルで、千葉大学肺がん治療センター呼吸器外科渋谷潔先生が講演されました。気管支鏡や手術検体の細胞診断を説明されました。
また同様に『呼吸器内視鏡検査時の迅速細胞診(ROSE)における人工知能(AI)画像解析システムの開発』を、国立がん研究センター中央病院内視鏡センター古瀬秀明先生が、ご苦労されている開発を述べられました。
今は顕微鏡を覗くことは少なくなりましたが、大変興味深かったです。過去にかなり細胞を見て専門医を取得しましたが、今後は人間でなく間違いなくAIが活躍する分野になるだろうと思います。他に『呼吸器感染症と気管支鏡』のタイトルで日本赤十字社医療センター呼吸器内科栗野暘康先生が、各種感染症の重要ポイントを述べられました。
さらに『日本における肺がん検診の現状と展望』のタイトルで、東北大学呼吸器外科客員教授佐川元保先生が、特に胸部CTにおける小結節のガイドラインを説明いただきました。



-
7月24日(木)は、『加齢と咳反射低下』のタイトルで、済生会富田林病院の岩永賢司先生が講演されました。加齢による咳反射低下と誤嚥性肺炎の関係などを述べられました。

-
7月26日(土)は、第117回日本内視鏡学会近畿支部会が大阪市内で開催されました。
病院医師を主体とした気管支鏡における活発な学会でした。クリニックではもう気管支鏡検査をしませんが、珍しい報告例を多くお聞きしました。この暑い中でも、学会が終わっても会場から最寄り駅まで歩きながら、気管支鏡のことを論議している若い医師たちもいて、私も古兵としても負けてられないと思いました。
-
7月31日(木)は、webにおいてAIセミナーの2題の講演を視聴しました。まず『AIで変わる胸部X線画像診断』のタイトルで、杏林大学放射線科教授の横山健一先生が講演されました。次に三鷹市の肺がん検診において既にAIを導入されている様子を担当医師から説明されました。AIの検診実力は半人前ではないですが、平均は0.8−9人前で、時に1.3人前にも化けることがあるとの印象でした。すごく指摘できるところもありますが、もう一つのところもあり、今のところ人間の目と相互に読影する必要がありそうです。しかしもう1年後にはAIだけでの読影で、肺がん検診は十二分になると想像します。

ふなこし呼吸器内科 院長 船越俊幹